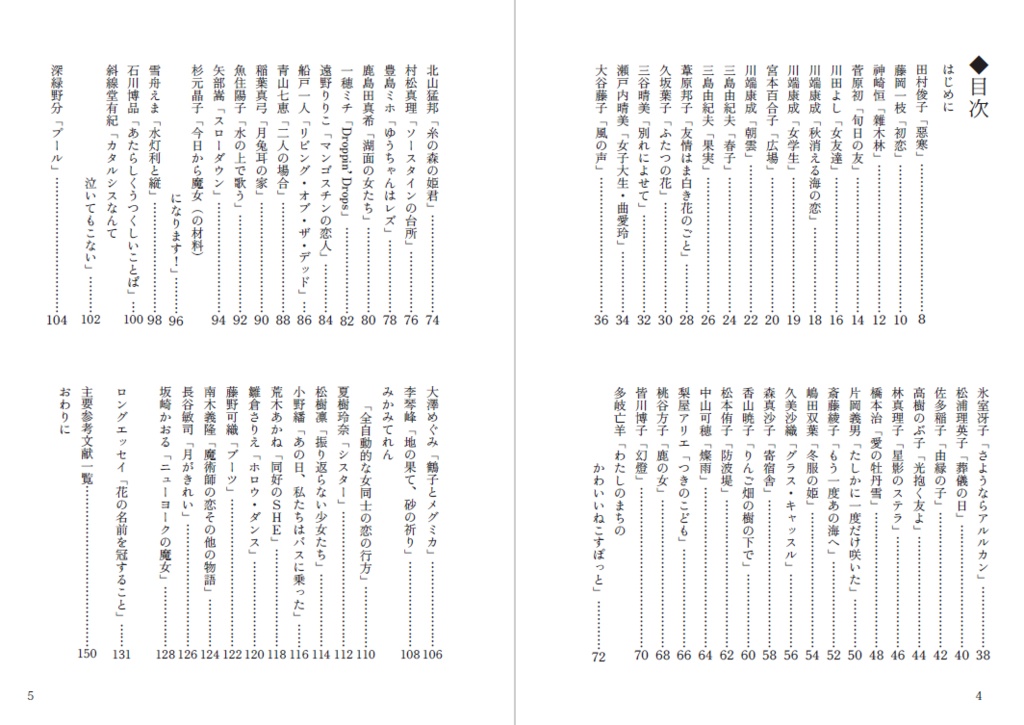百合小説アーカイヴ(仮)
- 物販商品(自宅から発送)あんしんBOOTHパックで配送予定支払いから発送までの日数:10日以内在庫なし¥ 1,130
「語られる場のなかったがゆえに、忘れ去られてしまった〈百合〉と呼べるはずの短篇群があります。わたしがとりあげたいのは、このような小説たちなのです」絶版本をはじめ、単行本未収録や全集でしか読めなかった、果ては国立国会図書館の蔵書にない作品まで、一世紀を越える日本文学史を歩く、ブックガイド・レビュー集。 わたしたちのアーカイヴ事業は、 いまだ(仮)のままに開始される。 補遺「花の名前を冠すること」を併録。 -- 表紙イラスト:伊勢海老ボイル -- 【推薦文:坂崎かおる&南木義隆】 〈坂崎かおる 推薦コメント〉 界隈では有名なのかもしれないが、女性同士に関する「百合」の語源を紐解くと、『薔薇族』の編集長であった伊藤文学の造語という説が、初出としては確度の高いものだろう。1970年代に、女性読者の投稿欄として、「百合族の部屋」が設けられたとされている1。伊藤がなにをきっかけとして設けたかは詳らかではないが、『薔薇族』自体への関心が女性読者に多いことを伊藤は記しており2、彼女たちの同性愛への捉え方に鋭く反応したのかもしれない。時代が下る中で、「百合」という言葉は、日活の映画に代表されるような、性愛が強めのイメージをもたれるが、「マリ見て」などの2000年代の作品を通じていくなかで、大正時代の「エス文学」に近いような形式に変化しているように個人的には思う。いずれにせよ、公に表出しづらかった言葉が、現代に「百合小説」「百合アニメ」などとして市民権を得ていく変遷は興味深い。 伊藤は「薔薇」の対比として「百合」を選んだ理由を、「百合はほら、ナルシシズムの象徴だから」と述べている3。年数が経っている上での発言として勘案する必要があるが4、彼自身が、女性同士の関係を「ナルシシズム」と捉えていることは示唆的だ。その自己愛的な捉え方は、本書で織戸氏が冒頭に挙げている田村俊子の考えに近くはないだろうか。田村は「同性間に感じる一種の友情」は、彼女たちにとって「危険のない結構なおもちゃ」だと記している(本書9ページ)。百年近く隔てた両者の間に、「百合」に対する考えが似通っている点は見逃せない。「変遷」を見ていく視点には、「変わらないもの」を捉える視点も必要だ。 その意味で、今回の織戸氏の「百合小説アーカイブ(仮)」の挑戦は、新たな視座を築くもののひとつだろう。本書には、こういった論評に必ず出てくる吉屋信子や長野まゆみといった作家は登場しない。どちらかというと、これまで「百合」の文脈の中では取り上げられにくかった作家や作品を意図的に選んでいることがうかがえる。「百合小説」を論じる際は、多くの文学研究と同様に、「何を選び」「何を選ばなかったか」が重要となる。多くの研究*5が、戦前から戦後にかけての女性同士の同性愛を捉える際に、ハブロック・エリスらの説の広がりを指摘しているが、挙げられている作品を見ると、そのような解釈に収まらない、「百合」の萌芽が垣間見れるように思う。 氏自身も、「対象とする作品数が足り」ないとしており、挙げられた作品を貫くような仮説が欲しいところではあるが、これを嚆矢として、新たな「百合小説」研究が広がることを願っている。 *1「1976年11月号から女性読者のページ「百合族の部屋」が掲載されている」(前川直哉(2014)「1970年代における男性同性愛者と異性婚」『セクシュアリティの戦後史』(京都大学学術出版会)P205) *2「薔薇族を理解しようとする女性たちが増えている」(『新評』1975年9月号 P58) *3「「いま気にかかっているのは少年愛のこと」ゲイ雑誌『薔薇族』の初代編集長 」ニコニコニュース2011年10月30日(アーカイブのみ) https://web.archive.org/web/20120316045029/http://news.nicovideo.jp/watch/nw137585/2 *4「百合族」という言葉自体も、コーナー開設当時は、必ずしも女性同性愛者だけを指してはおらず、定義がはっきりしていなかった。(赤枝香奈子(2010)「百合」『性的なことば』(講談社現代新書))。なお、「百合」という言葉の変遷についてはこの論考が詳しい。 *5 例えば趙書心(2002)「女性解放とレスビアニズムの間 : 『番紅花』における女性同性愛言説をめぐって」『名古屋大学人文学フォーラム』(名古屋大学大学院人文学研究科図書・論集委員会)、赤枝(2014)「戦後日本における「レズビアン」カテゴリーの定着」『セクシュアリティの戦後史』(京都大学学術出版会)など * * * 〈南木義隆 推薦コメント〉 私が小説を書き始めた十五年前に百合を題材とすることは、純粋な作品数の少なさ、レーベルは立ち上げられどすぐに消える状況を前に──風が吹けば飛ぶおぼろげな足跡を頼りに夜の砂漠を歩き、ところどころに生える木に生る果実があれば喜び勇んでもぎ取り、味わい、辛うじて喉を潤したつつ、たどり着いたところで湖は枯れ果てているかもしれないという恐れと、逆説的にその恐れによって分泌する脳内麻薬によって「この先には人類未踏のシャングリラが待っているに違いない」という誇大妄想的なナチュラルハイを行き来していました──しかし現在の私が、つまり百合を冠した小説アンソロジーに中短編を寄せ、単行本の帯に百合とクレジットする新人小説家に見えるのは、各々が確保した土地に水を引き、鍬で土を耕す地平です。 百合小説は色々な出版社から時に一般文芸として、時にライトノベルとして、断続的なリリースが続いています……少なくとも、今のところは。たどり着いたのは夢想したシャングリラでも、恐怖した干上がった湖でもなく、適切な天候を期待しつつ、干ばつやイナゴの襲来を危惧する極めてリアリスティックな場所でした。 私たちは──大なり小なり百合を志向する小説の書き手は──そこで確実かつ安定した収穫を得て、この土地が文芸の世界にとって意味ある、豊穣の地であることを証明する必要に迫られるフェーズに至っているでしょう。 翻って本書『百合小説アーカイブ(仮)』のリストのなかには、かつての私が夢見るパラノイアックな旅路において、しばしば立ち寄った散発的に生える木に実っていた果物としての作品の名が幾つか並んでいます。それらの題名をこうして改めて並べて見直すと、手に触れたときの瑞々しさがありありと思い起こされました。 けれども同時に、私には見知らぬ名の方が圧倒的に数多いことを白状せねばなりますまい。このリストの作成者は、収穫したての果実を容易にスーパーマーケットで購入できるこの時代において、あえて砂漠へと舞い戻り、広大な地平線を散策し、あまりにも多くの木々を、オアシスを発見しています。どれほどの渇きの果てに至ったものかと空恐ろしくなるほどに。 本書は百合小説不毛の時代をサバイブした十五年前の私に渡せば狂喜乱舞したであろう、まるで魔法の地図のようなガイドブックです。 どんな芸術、エンターテイメント、表現様式においても、その分野が意義深く探求する価値があると証明するのは、時の洗礼によってクラシックとして位置付けられるに至った作品群の力強さではないかと思います。 本書の意義深さとは、百合小説が断続的にリリースされる二〇二三年において、この時代が決して突然変異の起きた特異点ではなく、朧気であっても、蜃気楼ではなく、確かに積み重ねられてきた美しい欠片──実際の創作者の意識の方向はひとまず置いておくとして──があったことで成立せしめたということを明確な形にした点ではないでしょうか。 以上の文言はあくまで百合小説の書き手としての立場に則ったもので、百合小説の読み手としては「このリストを制覇するぞ!」という純粋な喜びに満ち溢れていると最後に付言しておきます。 * * *